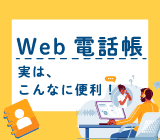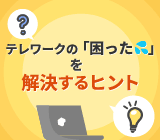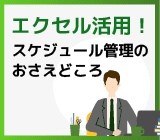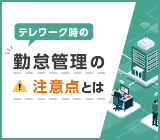
失敗しない! ワークフローシステム導入で起きがちな問題点とその対策
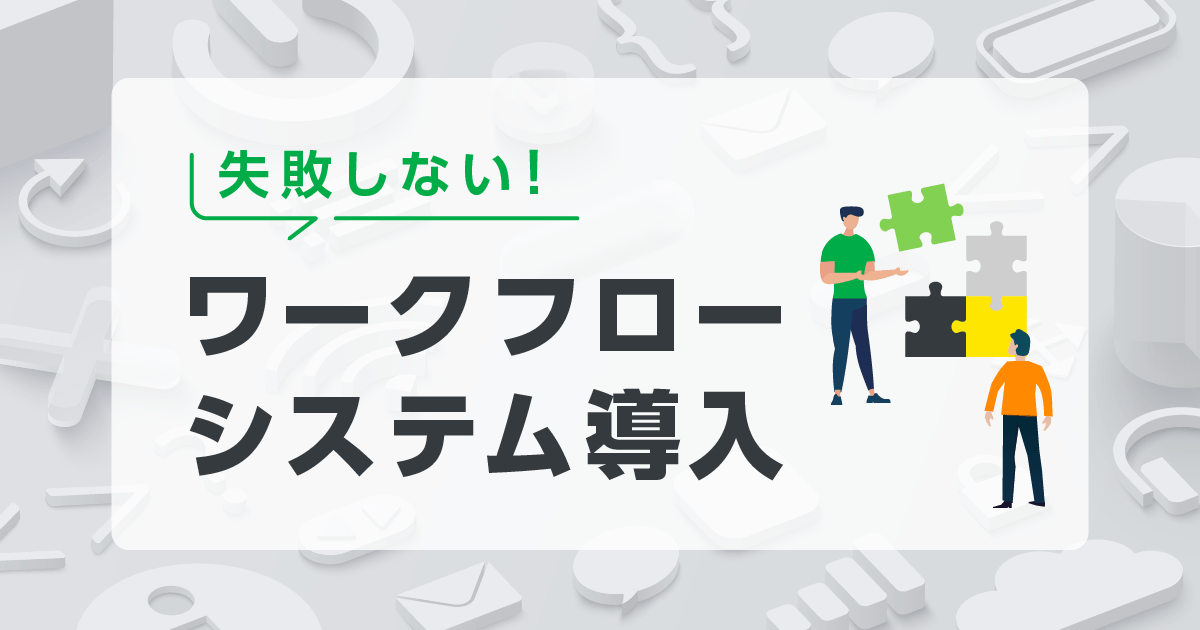
社内の業務プロセスを電子化し、場所を選ばずに申請・承認を可能にするワークフローシステムは、企業の業務効率化に大きく貢献します。
しかし、導入を検討する一方で、失敗のリスクを懸念してなかなか踏み切れない企業も少なくありません。本記事では、ワークフローシステム導入時によくある失敗事例、その原因、そして成功に導くための具体的な対策について詳しく解説します。
ワークフローシステム導入で起こりがちな失敗

ワークフローシステムを導入した際に頻繁に起こる失敗の一つに、社員が新しいシステムに馴染めないという問題が挙げられます。 「以前のやり方の方が楽だった」 「かえって手順が増えて複雑になった」 といった理由から、システムが社内に浸透しないケースがあります。
新しいシステムの操作が複雑であれば、一部のメンバーしか使いこなせず、他の社員がシステム利用を避ける状況も発生し得ます。システムの操作方法に関する研修や教育が不十分な場合、せっかくの便利な機能も活用されないままになってしまうかもしれません。
また、業務フローの変更や人事異動に伴う設定変更の手続きが面倒で、結果的に放置されてしまうというケースも見られます。
ワークフローシステム導入後に問題が起こる主な原因
ワークフローシステム導入後に問題が発生したり、システムをうまく使いこなせなかったり、社内に浸透しなかったりするなどして、結果的に導入コストに見合った効果が得られない原因は複数存在します。
ここでは、その主要な5つの原因について説明します。
自社の業務に適したシステムを選定できていない
1つ目の原因は、自社の業務に合致したシステムを選べていないことです。紙による申請作業の方法は、企業や業務内容によって多岐にわたります。
例えば、複数の承認者が必要な場合や、複数の承認ルートが存在する場合など、申請方法はそれぞれ異なります。社員のニーズを考慮することも重要です。営業職が多い職場では、外出先からスマートフォンで申請や承認の確認を行いたいというニーズがあるでしょう。
自社の申請方法やニーズに合わないワークフローシステムを選んでしまうと、結局うまく活用できず、導入の意味がなくなってしまいます。外部のワークフローシステムを導入する際は、自社に最適なものを選ぶか、あるいは自社の状況に合わせて柔軟にカスタマイズできるシステムを選ぶことが大切です。
導入準備が不十分だった
2つ目の原因は、導入までの準備が不十分だったことです。ワークフローシステムを導入するためには、現在行われている業務プロセスを一度すべて洗い出し、それを新しいシステムに組み込む作業が必要です。
この作業が不十分だと、せっかく導入したシステムも十分に機能させることができません。また、洗い出した業務をそのままシステムに実装するだけでは、業務効率化の実現は難しいでしょう。業務を洗い出した上で課題点を見つけ、改善策を講じてから実装しなければ、無駄な工程がそのまま残ってしまいます。
もちろん、不備に気づいた場合は、後からシステムをカスタマイズし直すことは可能です。しかし、システムが稼働した後にやり直すのは手間がかかります。導入前にしっかりと準備を行い、自社の業務に合わせて設定しておくことで、導入後もスムーズにシステムを活用できるでしょう。
ちなみに、ワークフローシステムのカスタマイズとは、画面の項目の追加や削除、承認ルートや分岐の変更などを行うことです。どこまでカスタマイズが可能かはシステムによって様々で、中には人事異動への対応や申請フォーマットの作成、外部システムとの連携 (API) なども可能なワークフローシステムもあります。
カスタマイズの自由度が低いシステムを選んでしまった
3つ目の原因は、カスタマイズの自由度が低いワークフローシステムを導入していることです。一度システムを自社の状況に合わせて設定しても、退職や人事異動といった人の動きや業務内容の変更が発生すると、その都度カスタマイズし直す必要が生じます。
そのため、カスタマイズの自由度が低いシステムや、カスタマイズ自体が難しいシステムを導入してしまうと、スムーズに変更ができず、後々問題になる可能性があります。
カスタマイズ操作が難しく、できる人が限られている場合もあります。この場合、カスタマイズ作業の負荷が特定の人に集中してしまい、かえって業務効率が悪化してしまうことも少なくありません。
カスタマイズに多くの時間を要すると、変更対応が遅れてしまい、社員が慣れ親しんだ従来の紙ベースの方法に戻ってしまうこともあり得るでしょう。
外部連携が十分にできない

4つ目の原因は、社内で頻繁に使用しているグループウェアや経費管理システム、人事システムなどとの連携が十分にできないことです。
外部システムとの連携機能が不足していると、それぞれのシステムを立ち上げて数字などを手動で入力 ・ 転記しなければならず、社員の負担が増大します。
これにより工数や社員の負担が増加すれば、業務フローを電子化した意味が失われてしまいます。既存のシステムとの連携ができず、データを改めて入力する必要がある場合、その分の時間が取られるだけでなく、人為的なミスが発生しやすくなるというリスクも伴います。
直感的な操作ができず 「誰でも使える」 ものではない
5つ目の原因は、直感的な操作ができず、誰もが簡単に使えるシステムではないことです。
ワークフローシステムは組織全体で導入するシステムであるため、ITリテラシーのレベルに関わらず、すべての社員が使いやすいと感じるものでなければなりません。直感的な操作ができず、使い方を覚えるだけで大変なシステムでは、現場の社員は利用をためらってしまうでしょう。
操作が簡単で誰もが使いやすいシステムであるほど、社内に早く定着し、最大限に活用することが可能になります。
ワークフローシステム導入を成功させるポイント
ワークフローシステム導入にあたって、これまで取り上げてきた問題を回避するにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、システムを現場に浸透させて、本来の目的である業務効率化を実現させるためにできることを2つ紹介します。
【1】 導入準備を入念に行う
まず最初に、システムの導入準備をしっかりと行うことが挙げられます。
導入準備として、現在行われている申請や承認のルールなどを洗い出し、問題点を明確にしておくことが重要です。その際には、形式的なルールと実際の運用との間に乖離がないかどうかも詳細に調査しておきましょう。
申請者や承認者から困っている点をヒアリングしたり、改善に関する意見を求めたりするのも有効です。申請書類の提出状況や、提出から決済までに要する期間なども確認しておくことで、スムーズな承認プロセスを妨げている要因を見つけやすくなります。
こうした調査によって不要な業務やルールが明らかになった場合は、システムに実装する前に思い切って削減することを検討しましょう。導入前のこうした作業や調査は大変な労力を要しますが、社内の業務フローを包括的に見直し、改善する絶好の機会でもあります。
大きな業務改革に取り組んでいるという意識を持ち、導入準備を入念に行うことが成功への鍵となります。
【2】 現場に浸透するよう社員への説明を徹底する
2つ目のポイントは、新しいシステムが円滑に受け入れられるよう、社員に適切に説明し、導入しやすい土壌を整えることです。
もちろん、システムに慣れていない社員にも抵抗なく受け入れてもらうためには、最初から使いやすいシステムを選ぶことが重要です。しかしそれに加えて、社員に対してシステム導入の目的やメリットを明確に伝え、具体的な使い方を教育することで、システムを受け入れやすい環境を構築することが不可欠です。
研修プログラムなどを通してワークフローシステムについて十分に教育しておくことで、新しいシステムが現場に浸透しやすくなります。運用が開始された後も、システムの利用に関して不明点がないか随時確認するなど、社員への継続的なサポートを忘れないようにしましょう。
失敗しない! 自社に合ったワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムの導入を成功させるためには、自社に合ったシステムを選定することも大切です。
最後に、システムを選ぶときに考えたい4つのポイントを紹介します。
【1】 オンプレミス型かクラウド型か
まず最初に決めておきたいのは、オンプレミス型かクラウド型かという選択です。
オンプレミス型とは、システムの構築 ・ 運用を自社で行う形態を指します。このタイプは、自社の特定のニーズに合わせてシステムを構築できるため、カスタマイズ性が高いというメリットがあり、業務に完璧に合致したシステムを構築することが可能です。ただし、初期費用が高額になりがちで、開発、メンテナンス、運用をすべて自社で行わなければならないというデメリットもあります。
一方、クラウド型は、サービス提供事業者がインターネット経由でシステムを提供する形態です。インターネット環境があればどこからでもログインでき、初期費用が比較的安い点が魅力です。また、アップデートや障害が発生した際の対応を自社で行う必要がないというメリットもあります。しかし、一般的にカスタマイズ性はオンプレミス型よりも劣るというデメリットも考慮する必要があります。
【2】 誰でも直感的に操作できるか
2つ目に、誰もが直感的に操作できるかどうかを確認することが重要です。
操作方法などを共有する社内教育は不可欠ですが、システムの UI (ユーザーインターフェース) が使いやすいことも同様に重要です。システム担当者だけが使いやすい状態では、現場全体への浸透は難しくなってしまいます。
特に、社外での利用が多くなりそうな場合は、スマートフォンやタブレットから見たときに視覚的にわかりやすいかどうかを必ず確認しておきましょう。
【3】 どの外部システムと連携できるか
3つ目に、自社にすでに定着しているシステムに対応できるかどうかをしっかりと確認しておく必要があります。
外部システムとの連携が可能なワークフローシステムは多いですが、最も重要なのは、自社がすでに導入している既存のシステムとの互換性です。
これまで使い慣れていたグループウェアやシステムを、新しいワークフローシステムに合わせて変更するのは、多大な手間と労力を伴います。業務自動化の恩恵を最大限に享受するためにも、他のシステムとスムーズに連携できるものを選ぶようにしましょう。
【4】 カスタマイズはしやすいか
最後のポイントは、カスタマイズの自由度と難易度についてです。
一度ワークフローシステムを導入しても、人事異動によって承認者が変更になるなど、業務フローの変更は必ず発生します。カスタマイズにプログラミングなどの専門知識が必要なシステムでは、一部の限られた社員しか変更作業を行うことができず、その社員の業務を圧迫してしまいます。
さらに、その社員が退職してしまえば、誰も変更手続きができなくなるという事態も起こりかねません。カスタマイズの自由度の高さと、操作の難易度の低さは、システム選定の際に必ず確認すべき重要なポイントです。
使いやすいワークフローシステムなら 『rakumo ワークフロー』

使いやすいワークフローシステムを探しているのであれば、 「rakumo ワークフロー」 の検討をおすすめします。
多くの企業で利用されている Google Workspace との連携が可能であり、システム担当者でなくてもカスタマイズが容易な簡単設計が特徴です。
誰もが使いやすい直感的なUIが採用されているため、多数の社員を抱える大手企業にも採用されています。スマートフォンでも見やすく操作しやすい 「rakumo ワークフロー」 を、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。